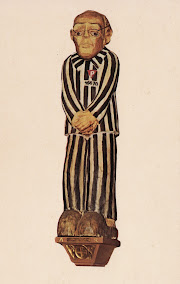岩下壮一とG.K.チェスタートン
若松英輔氏の講演に影響されて、岩下壮一神父著『信仰の遺産』を手に取った。ずっと以前に購入していたが、読まないままになっていた。文庫本の小さい文字は白内障も緑内障も進行中の私には読みづらい。どこかとっかかりがないかと、目次を眺めていたら、G.K.チェスタートンの名前が見つかった。 私は大学生の頃、チェスタートンを愛読していた。といっても、Father Brown という神父が主人公の探偵小説のシリーズだけだった。3年次だったと思う。Essay という通年講座で、年度内に100篇のエッセイを読み、その一つ一つについてコメントを書いて出すという課題が出された。私はチェスタートンの短いエッセイ集を選んだ。すごい量の宿題だったので、そのことだけが記憶に残っているが、内容については、なにも残っていない。 『信仰の遺産』中のチェスタートンの名前に惹かれて、その章を読み始めた。冒頭の数行は次のようである。 「チェスタートンは私の座右の書ではないがここ十年来の枕頭の書である。一日の仕事に疲れた頭と心とを医す一番いい慰安は床の中にもぐり込んで枕頭のチェスタートンを読むことである。そこに私は自分に最快適な世界を見出す。私を悩ますあらゆるコンプレクススは彼の明快な議論とユーモアとによって解消する。若しもこんな夜更けに私の寝室を窺う盗賊があったとしたら、彼は気違いの家に紛れ込んだと思うに違いない。私は彼を読みつつ幾度か深夜の寂寞を破って、ひとりで哄笑、爆笑をすら禁じ得ないことがある。それほど彼は私を愉快にしてくれる。」 チェスタートンについて書いたとき、岩下神父はハンセン病療養所の神山復生病院の院長であった。「ある患者の死」という章では、患者の苦しみを見殺しにするしかない現実に直面して、「プラトンもアリストテレスもカントもヘーゲルも皆、ストーブの中へ叩き込んでしまいたかった」と書いておられる。 そのように厳しい現実の中で、ささやかな楽しみをチェスタートンに見出しておられたことに、ホッとさせられる。「こんな面白い本を皆よんで了ってはあとの楽しみがなくなっては困ると思うから、急いでよんだりしたことはない。」とまで書いておられる。 残念ながら、『信仰の遺産』を通読することはできなかった。でも、神父の生き方そのものに魅力と深い感銘を受ける。